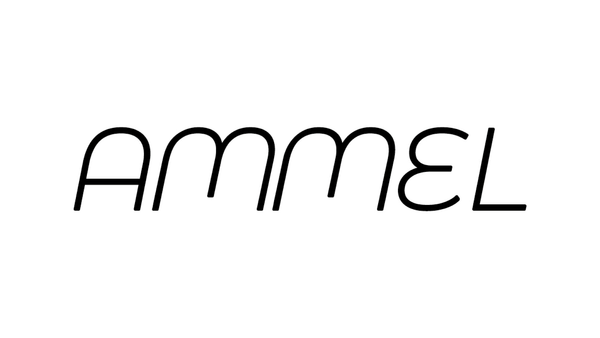ボレスワフ・プルスによる、あまり知られていないポーランドの童話
遠い昔、水がなめらかな石の上を自由に流れ落ちていた時代、小川は大地を削りながら流れていた。
しかし今では、その小川は春の雪解けや激しい豪雨のときにしか目を覚まさない。
その古い川床の下には、大きく滑らかな岩が横たわっていた。それは、まるで何かの秘密を封じ込めているかのようだった。そして実際、その岩の下には異界への入口が隠されていた。そこは、想像を絶するほどの財宝を守ると言われる秘密の世界。世界そのものが理解しえないほどの富が眠っていた。
そこでは、黄金の寝台の上に、伯爵夫人のように豪奢な衣装をまとった乙女が眠っていた。
だが、この乙女は呪われた深い眠りに囚われていた。彼女の頭には黄金のピンが打ち込まれていたのだ。それが恨みによるものなのか、恐れによるものなのか、それとも忘れ去られた儀式の一環なのか、誰にもわからなかった。ただ、彼女を救うには、そのピンを引き抜き、彼女と結婚しなければならない。しかし、それは容易なことではなかった。その洞窟には恐ろしい怪物たちが巣食い、乙女とその財宝を守っていたのだ。彼女の美しさや輝く黄金を求める勇敢な者たちでさえ、その深淵の恐怖に怯え、手を出せずにいた。
この伝説は、代々ささやかれ、語り継がれてきた。復活祭や聖ヨハネの日には、岩が転がり、勇気ある者が小川のそばに立てば、闇へと開かれた入口とその奥の輝きを垣間見ることができた。
ある復活祭の日、ザスワヴルの若い鍛冶屋が、小川のほとりに立っていた。彼はハンマーとふいごを扱う日々に疲れ果てていた。
彼の鍛えられた眼差しは、川の水底に広がる暗がりを見つめるうちに、次第に柔らかなものへと変わっていった。
「もしこの財宝が手に入れば……」
彼は呟いた。
「ひとつかみでもあれば、この苦しい労働の日々から解放されるのに……」
すると、まるで彼の願いに応えるかのように、岩が静かに動いた。
そこには、金銀財宝が山のように積まれ、銀の杯や王宮にふさわしい豪奢な衣が輝いていた。しかし、彼の視線を釘付けにしたのは、その財宝の中心に横たわる乙女だった。
彼女の美しさに、鍛冶屋は息をのんだ。彼女の瞳は閉じられたままだったが、涙が静かに頬を伝い、その雫が衣や黄金の寝台、冷たい石の床に落ちるたびに、宝石へと変わっていった。
彼女は、深いため息をついた。その音は、あまりに悲しみに満ちていて、木々を揺らす風でさえもそれに共鳴し、震えたほどだった。
鍛冶屋の心臓は激しく鼓動し、彼は一歩踏み出そうとした。しかし、その瞬間はあまりにも短く、再び岩は静かに閉じてしまった。ただ、小川が小さく泡立ちながら、最後の囁きを残しただけだった。
それ以来、鍛冶屋は平穏を失った。
乙女の姿が彼の脳裏から離れず、涙に濡れた彼女の顔が瞼に焼きついてしまったのだ。鍛冶場で働いても、炎の輝きは色あせ、鉄を打つ音は遠くかすんで聞こえた。彼の心は焦がれるような思いに蝕まれ、まるで溶けた鉄のように身を焼かれた。
耐えきれなくなった彼は、ある老いた薬草師のもとを訪ねた。
銀貨を彼女のしわがれた手に握らせ、助言を乞うた。
「たったひとつの方法がある」
薬草師は、悟りの影を帯びた目で言った。
「聖ヨハネの日に戻り、岩が開くのを待て。そして、深淵へと入るのだ。彼女の頭に打ち込まれたピンを抜けば、彼女は目覚める。結婚すれば、お前は計り知れない富を得るだろう。ただし、よく聞きなさい。怪物たちが襲いかかり、恐怖が心を蝕もうとするときは、十字を切り、神の名を呼ぶのだ。恐れは奴らに力を与え、勇気はそれを封じる」
「恐怖が支配するとき、どうすればわかるのですか?」
鍛冶屋が尋ねると、老婆は乾いた笑いを漏らした。
「深淵へ踏み出せば、すぐにわかるさ」
二か月の間、鍛冶屋は小川のそばで決意を固めた。まるで焼き入れされた鋼のように。
そして、聖ヨハネの日、太陽が頂点に達したとき――岩が開いた。
彼は斧を握りしめ、暗闇の中へと飛び込んだ。
そこには悪夢のような怪物たちが潜んでいた。狼ほどの大きさの翼を持つ蝙蝠が嵐のように飛び交い、石臼ほどの巨大なヒキガエルが道をふさいだ。蛇が闇を這い、鋭く鳴き声を上げながら彼の足に絡みついた。狼たちは炎のように光る目で睨みつけ、泡を吹く口からは燃え盛る炎が滴り落ちた。
怪物たちは彼を取り囲み、叫んだ。
「お前はここで死ぬのだ、鍛冶屋よ!」
だが、彼は怯むことなく、斧を握りしめた。その手は白くなるほど強く締められていた。
ついに、彼は黄金の寝台へとたどり着いた。その周囲では、闇の使者たちさえも彼女に手を触れることはできなかった。
彼は乙女の頭に打ち込まれた黄金のピンを握りしめ、引き抜こうとした。
その瞬間、彼女の額から血が流れ出し、彼女の目がぱっと開いた。そして、彼の服を掴み、か細い声で問いかけた。
「なぜ私を傷つけるの、見知らぬ人よ?」
恐怖が、冬の冷気のように彼の体を駆け抜けた。
彼の手がわずかに震えた――その一瞬のためらいを、怪物たちは見逃さなかった。
最も大きな口を持つ怪物が襲いかかり、彼の体を切り裂いた。
血が飛び散り、石壁を赤く染めた。
その瞬間、岩は轟音を立てて閉ざされた。
それ以来、小川はほとんど干上がり、乙女の泣き声は地の底に閉じ込められたままだった。
だが、その悲しみの声は今も風に乗り、野や森をさまよい続けている。永遠に。